日々の業務に生まれる“すれ違い”
現場では、職種の違いや経験年数の差から、さまざまな意見が飛び交います。
ケアの優先順位や利用者様への対応方法など、ちょっとした判断の違いがすれ違いにつながることも少なくありません。
気持ちが高ぶる場面では
忙しい時や急な判断が求められる場面では、どうしても自分のやり方を主張したくなります。
そんな時に役立つのが、「相手の立場を想像する」という視点です。
新人とベテラン、それぞれの背景
たとえば新人の方であれば、不安や慎重な気持ちが言動に表れることもあります。
一方で、ベテランの方なら、過去の経験や安全への配慮が発言ににじむこともあるでしょう。
話を聞くことから始めてみる
まずは、最後まで話を聞くことが大切です。
途中で遮らず、「なぜそう思うのか」と問いかけながら進めていくことで、相手の考え方や価値観が見えてきます。
歩み寄りの工夫を
自分の案と相手の案、どちらにも良さがあると感じたときは、折衷案を作るのもひとつの方法です。
また、「聞く姿勢」そのものが信頼の土台となり、関係を育てていきます。
目的を共有することの大切さ
意見が違うことは悪いことではありません。
異なる視点が交わることで、新しい気づきや解決策が生まれることもあります。
大切なのは、「どうすればより良いケアができるか」という共通の目的を持つことです。
視野を広げるきっかけに
かいご姉妹サロンでは、他の施設での工夫や考え方に触れることができます。
違う立場の人の声を聞くことで、自分の視野が広がるかもしれません。
意見をすり合わせていく過程は、決して妥協ではなく、協力の一歩となるのです。


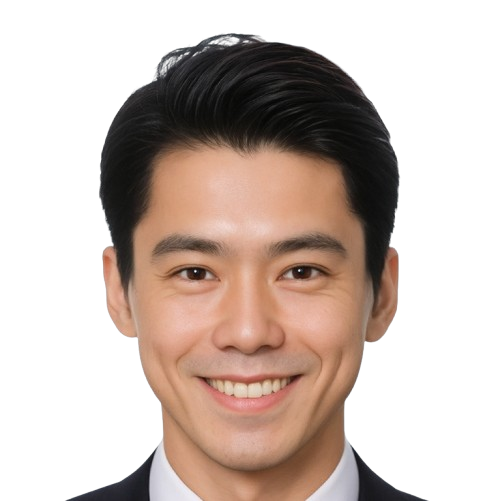





コメント